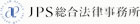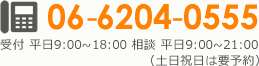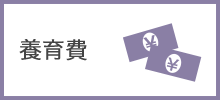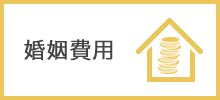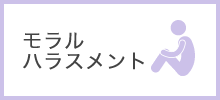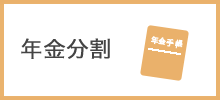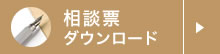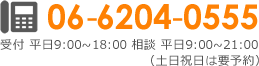【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
養育費・婚姻費用の算定表が新しく改訂されました!

1 養育費・婚姻費用算定基準・算定表の改訂
養育費・婚姻費用の決定にあたっては、最高裁判所が発表している養育費・婚姻費用算定表が使用され、これが実務上非常に重要な基準とされてきました。もっとも、従来の算定表は、平成15年月に公表されたもので、これが公表されてから15年余りが経過し、近年は「社会情勢が変化し、現在の生活実態にあっていない」などと指摘されていました(多くは養育費・婚姻費用が安すぎるという声)。
このような背景から最高裁判所は平成30年度から研究を開始し、令和元年12月23日、養育費・婚姻費用の算定に関し、新たな基準を採用し、新しい算定表を発表しました(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)。
なお、日本弁護士連合会でも平成28年に独自の算定表を作成しましたが、これは家庭裁判所の実務では取り入れられていませんので、インターネット等での検索では注意が必要です。
2 具体的な改定額
では、改訂された新算定基準では、養育費・婚姻費用は、具体的にはどの程度の金額、また旧算定基準との差額になるのでしょうか。以下の家族構成を例に、旧算定基準と新算定基準とを比較してみます。
【家族構成】
夫 給与所得者
妻 専業主婦(年収0円)
子2人
第1子:17歳(15歳以上)、第2子:13歳(0~14歳)
①夫の年収500万円の場合
|
養育費 |
|||
|
|
旧基準 |
新基準 |
差額 |
|
算定表の該当欄 |
8~10万円 |
10~12万円 |
|
|
概算額 |
9万1000円 |
10万4000円 |
△1万3000円 |
|
婚姻費用 |
|||
|
|
旧基準 |
新基準 |
差額 |
|
算定表の該当欄 |
10~12万円 |
12~14万円 |
|
|
概算額 |
10万9000円 |
12万5000円 |
△1万6000円 |
②夫の年収1000万円の場合
|
養育費 |
|||
|
|
旧基準 |
新基準 |
差額 |
|
算定表の該当欄 |
16~18万円 |
18~20万円 |
|
|
概算額 |
17万3000円 |
19万8000円 |
△2万5000円 |
|
婚姻費用 |
|||
|
|
旧基準 |
新基準 |
差額 |
|
算定表の該当欄 |
20~22万円 |
22~24万円 |
|
|
概算額 |
20万7000円 |
23万7000円 |
△3万0000円 |
③夫の年収1500万円の場合
|
養育費 |
|||
|
|
旧基準 |
新基準 |
差額 |
|
算定表の該当欄 |
24~26万円 |
28~30万円 |
|
|
概算額 |
25万2000円 |
28万3000円 |
△3万1000円 |
|
婚姻費用 |
|||
|
|
旧基準 |
新基準 |
差額 |
|
算定表の該当欄 |
28~30万円 |
34~36万円 |
|
|
概算額 |
30万2000円 |
33万8000円 |
△3万6000円 |
以上の家族構成を例にしますと、いずれのケースでも養育費・婚姻費用は増額となりました。新算定基準を採用することにより、養育費・婚姻費用が安すぎるといった多くの声に応え、養育費・婚姻費用は増額されるケースが大半となりましたが(もっとも、必ずしもすべてのケースで増額になるわけではありません。)、数万円程度の増額に留まったもので、期待されていたほどの増額とはなってはいない印象です。
3 すでに旧算定基準で決定した養育費・婚姻費用への影響
上記のとおり、新算定基準によりますと、旧算定基準と比較して多くのケースで養育費・婚姻費用は増額となります。では、すでに旧算定基準で決定した養育費・婚姻費用について、新算定基準で算定し直し、養育費・婚姻費用の増額を主張することはできるでしょうか。
結論を言いますと、答えは「No」です。
この点について、前述した平成30年度司法研究における「研究報告の概要」の「8 事情変更について」において、最高裁判所は、「本研究の発表は、養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない。」と述べており、新算定基準を採用したことの一事では、すでに決定した養育費・婚姻費用を変更すべき事情変更には該当しないこと明確にしています。
4 養育費の終期
最後に、平成30年度司法研究においては、養育費・婚姻費用の終期と関連して、「成年」の概念にも言及しています。
家庭裁判所で養育費の支払いを定めた場合、養育費の終期について、「20歳」などと具体的な年齢を定めずに、「成年に達した日の属する月まで」と定める場合が少なくありません。「成年」は民法によって規定されますが、この度の民法改正により、2022年4月から「成年」が20歳から18歳に引き下げられることが決定しています。これに伴い、養育費の終期について「成年に達した日の属する月まで」と決定していた場合の「成年」(終期)が「20歳」のままなのか「18歳」に引き下げられるのかが問題となりましたが、これについて、最高裁判所は、『「成年」の意義は、基本的に20歳と解するのが相当である』と述べ、「成年に達した日の属する月まで」と定めた場合の養育費の終期について、18歳には引き下げられず、20歳のままであることを明言しました。