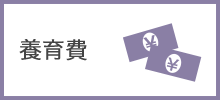【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
養育費
養育費とは
養育費とは、父母の離婚後に、未成熟子(必ずしも未成年の概念とは一致しません)が独立の社会人として成長・自立するまでに必要となる費用のことです。衣食住の費用はもちろん、教育費や医療費、そして小遣いなど適度な金額の娯楽費なども含まれます。
夫婦が離婚しても、子どもとの関係では、親子であることに変わりはありませんので、離婚後であっても、親は子どもに対して扶養義務を負います。したがって、離婚後、子どもを引き取らなかった親(被監護親といいます)は、子どもを引き取って養育している親(監護親といいます)に対し、養育費を支払うことになります。また、親子関係に基づいて支払われる金銭ですので、離婚の原因や親権者かどうかに関わらず、法律上の親である限り支払う必要があります。但し、監護親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合には、子どもと一緒に住むことになる養親(再婚相手)が一次的な扶養義務を負うことになりますので、子どもを引き取らずに離れて暮らす被監護親は、養育費の支払義務を負わなくてよくなる場合があります。
養育費の金額・算出方法
⑴ 養育費の金額
親は、それぞれの収入に応じて養育費を分担することになります。そして、養育費を決める場合の有力な基準になるのが、裁判所が公表している「算定表」です。
この算定表で養育費を決める場合、まずは両親の収入を基準にします。もっとも、収入以外の要素も考慮されています。収入の額面は同じでも、会社員などの給与収入か、自営業者の事業収入かによって、負担すべき養育費額は異なります。また、子どもの人数や年齢によっても養育費額は異なります。当然、子どもの人数が多い方が養育費の金額は高くなりますが、1人増えるごとに2倍、3倍と比例して増額されるわけではありません。年齢についても、0~14歳か15歳以上かによって金額が変わります(0~14歳<15歳以上)。
算定表は以下の要素を考慮して決められていることになります。
・両親の収入額
・両親の収入が給与収入か、事業収入か
・子どもの人数、年齢(0~14歳か、15歳以上か)
⑵ 養育費の算出方法
話し合いで養育費を決める際、その取り決めの方法に法律上のルールがあるわけではありません。あり得ない話ではありますが、極端な例で言えば、月収30万円の方が、30万円全額を養育費として渡すという約束をしても構いません。もっとも、通常は、両親の収入や財産、生活状況などを考慮して話し合いで決めます。
養育費が話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所へ調停を提起することになりますが、その際は、前記しました裁判所が公表している「算定表」を用いて決定されることがほとんどです。また、話し合いで養育費を決める際にも、この「算定表」が裁判所の手続きで使われるため、有力な基準になります。
インターネットで「裁判所 養育費算定表」と検索すれば、算定表はすぐに検索できますが、念のため、以下に養育費(婚姻費用)算定表のURLを添付しておきます。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
この算定表の使い方を若干説明しておきます。
①子どもの人数、年齢によって使う算定表を選びます。
②養育費を支払う側(義務者)の収入額を、給与収入か(外側)、事業収入か(内側)を選択して縦軸から選びます。
③養育費をもらう側(権利者)の収入額を、給与収入か(外側)、事業収入か(内側)を選択して横軸から選びます。
④②と③がそれぞれ交差する点が養育費の金額(幅のある数字)になります。
例えば、0~14歳の子ども1人、夫の収入:給与650万円、妻の収入:給与100万円といった家庭を例にしますと、算定表の6~8万円の真ん中くらいに位置しますので、養育費は月額7万円程度が基準となります。
養育費をもらえる期間(終期)
養育費を支払ってもらう期間も、金額と同様、まずは話し合いをします。「子どもの成人まで」が一応の目安とはなりますが(なお、民法改正により18歳で成人となりましたが、養育費との関係では成人は20歳と考えるのが一般的です。)、現在では大学への進学も一般的となったことから、大学卒業までと取り決めることも多いです。
子どもが高校を卒業して就職することもあり、この場合は、高校卒業までとすることもありますが、将来の大学進学も見据え、原則大学卒業の22歳までとしておき、大学に進学しなかった場合には18歳までとしたり、反対に、原則高校卒業の18歳までと決めておき、大学に進学した場合には大学卒業の22歳まで延長するといった取り決めをする場合もあります。
養育費の取り決めの流れ
⑴ 話し合い(協議)
前記しましたとおり、養育費の金額、支払期間について、まずは当事者間で話し合いをします。養育費は離婚の条件の一つとして、離婚前に協議される場合が多いですが、先に離婚をしてしまってから、離婚後に養育費を決めることもできます。もっとも、できる限り離婚の条件として決めた方がよいと考えます。
養育費の話し合いについては、双方の収入がわかる資料(確定申告書や源泉徴収票、給与明細など)を前提に、金額や支払期間を決めます。また、進学費用や急な怪我などによる治療費など不慮の出費についてどうするかも話し合いをしておいた方がよいです。
⑵ 調停→審判
双方の話し合いで養育費が決まらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。調停では、収入に関する資料をもとに、調停委員を介して話し合いを進めることになります。調停手続では、調停委員が双方の事情を聞いて、一定の金額を提示するなど解決策を提示してくれることもありますが、あくまで調停は家庭裁判所での話し合いの場ですので、双方が養育費について合意ができなければ、調停は成立しません。
調停でも話し合いが決まらない場合、離婚前に養育費が離婚の条件の一つとして話し合われている場合には、離婚訴訟を提起し、離婚訴訟の中で離婚の是非と一緒に裁判所に養育費も決めてもらうことになります。
一方、先に離婚を先行している場合には、調停不成立となると、自動的に審判手続に移行することになります。審判手続に移行した場合には、裁判官が必要な調査を行った上で一切の事情を考慮し、審判によって養育費を決定します。
⑶ 養育費の取り決めができた場合(公正証書の作成)
双方の話し合いによって、養育費を決めることができた場合には、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくべきです。この強制執行認諾付公正証書を作成しておけば、相手が養育費を支払わなかった場合、裁判手続を経ずに直ちに相手の財産について強制執行の手続きを取ることができます。
一方、調停や審判で養育費が決定した場合には、決定事項が記載された調停調書や審判書によって強制執行をすることができるので、別途公正証書を作成する必要はありません。
養育費の変更
養育費は、いったん取り決めをしたとしても、一切不変というわけではありません。養育費を支払う側(非監護親)の収入が大きく増減したなど、養育費を決めた際の事情に変更があった場合は、養育費の増額・減額を請求することができます。
⑴ まずは話し合い
養育費を決めた際の事情が変わり、養育費の金額の増やしてほしい、反対に、養育費を減額してほしいといった場合、まずは双方で養育費の増額・減額について話し合いを行います。
例えば、養育費を増額してほしい側は、子どもの授業料が上がった場合などは、授業料が上がったことが分かる資料を提供する、養育費を減額してほしい側は、源泉徴収票など収入が下がったことが分かる資料を提供するなど、話し合いを成立させるには、なぜ増額・減額が必要なのか、誠意をもって説明することが大切です。
⑵ 調停→審判
養育費の増額・減額について、話し合いが成立しない場合には、養育費を決定する時と同じように、家庭裁判所へ調停(養育費増額もしくは減額調停)を申し立てることができます。調停では、養育費の増額・減額を必要とする事情に関して、資料をもとに調停委員を介して話し合いを進めることになります。もっとも、調停があくまで家庭裁判所での話し合いの場であることから、養育費の増額・減額について、双方が合意できなければ、調停は成立しません。
調停が成立しない場合には、自動的に審判手続に移行することになります。審判手続では、裁判官が養育費の増額・減額に関する事情の変更について、必要な調査を行い、審判によって養育費の増額・減額について決定します。
⑶ 養育費の増額・減額が認められる可能性のある事情の変更
養育費の変更について、一度決めたものである以上、些細な事情の変更では養育費の変更は認められません。養育費を決めた当時、予見(予想)できなかった事情の変更が必要とされています。
①養育費の増額が認められる可能性のある事情の変更
・子どもの怪我や病気によって多額の医療費がかかる場合
・子どもの進学や授業料が増加した
・養育費をもらう側が働けなくなった
②養育費の減額が認められる可能性のある事情の変更
・養育費を払う側の収入が激減した
・養育費をもらう側が就職などで収入が大きく増えた
養育費を弁護士に依頼したほうが良いケース
⑴ 自営業の場合
給与所得者の場合は、養育費を決めるための基礎となる収入を決める際、源泉徴収票を確認すれば事足ります(具体的には、控除前の給与額である「支払金額」を基礎収入とします。)。
一方で、事業所得者(自営業者)の場合は、確定申告書を確認することになりますが、給与所得者のように一箇所だけ確認すれば事足りるわけではありません。事業の所得金額に、青色申告特別控除額や減価償却費を加えたり、また、社会保険料控除額を控除したりして、基礎収入を算出しなければなりません。このように、事業所得者(自営業者)の場合は、基礎収入の算出自体が給与所得者と比べて複雑で、どうしても離婚実務に関する知識が必要になります。さらに加えて、事業所得者(自営業者)の場合は、経費に関して、「節税対策」が施されて、実際に家計に消費される金額よりも課税所得が低く申告されている場合があります。このような場合は、同居中に家計として使われていた金額を主張立証したりして、基礎とすべき実際の収入を立証することになります。こうなると、もはや一般の方だけで対処するのは非常に困難ですので、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
⑵ 私立学校や大学の進学費用
「算定表」によって決めた養育費には、公立中学・高校に関する学校教育費のみが考慮されています。子どもが私立中学・高校に進学した場合や、大学に進学した場合の進学費用(それにまつわる塾代なども含みます)については、算定表で決めた養育費には含まれませんので、別途検討する必要があります。
離婚前に既に私立学校に通っていた場合や大学に入学していた場合には、養育費を支払う側も私立学校や大学に通うことを容認していたはずですので、収入に応じて、相応の額を負担してもらうことができるのが原則です。
一方で、離婚後に私立学校や大学に進学した場合には、当然に養育費を支払う側(義務者)が支払義務を負うとは限りません。この場合は、義務者が承諾していたかどうか、両親の収入や学歴、地位などから、進学を想定できたかどうかなど、一切の事情が考慮されて支払義務を負うかどうかが判断されます。離婚前に子どもの教育に関して夫婦がどのようなスタンスを取り、どのような行動をしていたか、また夫婦間のやり取りなど、整理して主張立証しなければなりません。
「算定表」には含まれない子どもの進学費用が問題となるケースは、弁護士に相談・依頼されることがおすすめしたいケースです。
⑶ ほかに被扶養者がいる場合
前配偶者との間に子どもがいる場合や、認知した子どもがいる場合など、夫婦間の子ども以外に被扶養者となる子どもがいる場合には、「算定表」で簡易に養育費を算出することはできません。この場合、「算定表」のもとになった標準算定方式によって計算することは可能ですが、計算方法は複雑で、一般の方では、残念ながら太刀打ちするのが難しいと言わざるを得ません。このようなケースも弁護士に依頼されることをおすすめします。
⑷ 養育費の変更(増額・減額)を請求する場合
養育費の増額・減額については、上記5に記載しましたが、養育費をいったん決めた以上、その変更を請求する場合、請求される側の抵抗は総じて強く、簡単には応じてもらえない場合が多いといえます。そのような場合、調停・審判手続に移行しなければならなくなります。
また、養育費の変更については、
①事情の変更
②事情の変更が予見できなかったこと
③事情の変更が当事者の責任でないこと
④従前の取り決めでは著しく公平に反すること
といった事情を主張立証しなければなりません。養育費の変更が認められるケースかどうかの見極めは非常に難しいので、専門知識を有する弁護士に相談してほしいケースです。
まとめ
養育費に関しては、裁判所の「算定表」を使って取り決めされることが多いため、弁護士の助力を必要としないケースもあり得ます。しかし、算定表を使うことが困難なケースや機械的に当てはめるだけでは養育費を決めることができないケースも多くあります。
当事務所は、養育費に関するご相談についても、初回1時間無料で対応させていただいております。養育費は大切なお子さまのためのお金ですので、後悔をしないためにも、少しでも疑問や不安を感じられた場合には、当事務所に相談していただきたいと思います。