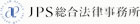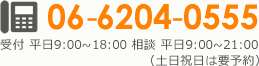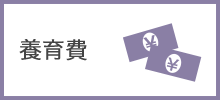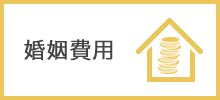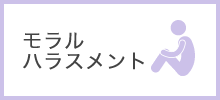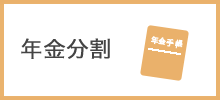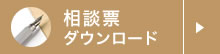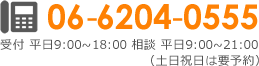【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別:離婚 ■理由:長期間の別居 ■依頼者:性別:女性 年代:50代 職業:派遣社員...
経営者の会社株式の財産分与について離婚に強い弁護士が解説
財産分与で不安を感じている経営者様へ
離婚時の財産分与で、経営する会社の株式まで取られてしまわないだろうか、悩んでいませんか?財産分与は、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を分ける手続きですが、会社の株式も対象となる場合がありますが、その評価方法や手続きは複雑です。
この記事では、経営する会社の株式が財産分与の対象となるケースとならないケース、具体的な評価方法、そして財産分与をスムーズに進めるためのポイントを弁護士が分かりやすく解説します。これを読めば、財産分与の際に、経営する株式に関する疑問が解消され、将来への不安を軽減できます。
具体的には、未上場株式、上場株式それぞれの評価方法、財産分与で揉めないための対策として婚姻前の契約や婚姻中の財産管理の重要性などが理解できるはずです。
適切な知識を身につけることで、離婚における財産分与を円滑に進めることができます。
-
1.財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を分けることです。共有財産には、預貯金、不動産、車、株式、退職金など、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産のすべてが含まれます。
一方で、婚姻前の財産や、相続・贈与によって得た財産は、原則として共有財産には含まれません。財産分与は、離婚成立後に請求することもできますが、期限は離婚から2年です。なお、財産分与は、法律上の権利であるため、相手が拒否した場合でも、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
1.1 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、原則として婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産のすべてです。典型的な対象財産としては、以下のようなものを挙げることができます。
・預貯金
・不動産(土地、建物)
・動産(車、家電製品、貴金属など)
・有価証券(株式、投資信託など)
・退職金(退職慰労金)
・生命保険の解約返戻金
・リゾートマンションやゴルフ場などの会員権
・仮想通貨
マイナスの財産である借金も、婚姻期間中に生活費や住宅ローンなど、夫婦で共有した目的のために作られたものであれば、財産分与の対象となります。
1.2 財産分与の対象とならない財産
一方で、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中でも、相続や贈与によって得た財産は、財産分与の対象とはなりません。
これらの財産は、夫婦の協力によって得られた財産とは言えないからです。ただし、相続や贈与によって得た財産であっても、婚姻期間が長かったり、夫婦共同生活に貢献していたりする場合には、一部が財産分与の対象となる可能性があります。
また、負債についても、ギャンブルや浪費など、個人的な目的で作った借金は、財産分与の対象外となります。
-
2.経営する会社の株式は財産分与の対象になるか
離婚時の財産分与において、経営する会社の株式がどのように取り扱われるかは、中小企業の経営者の方には大きな関心事のはずです。
会社の株式は、単純な預貯金とは異なり、その評価方法や財産分与への含め方について、様々な要素が絡み合います。
原則として、婚姻中に取得した財産は財産分与の対象となりますが、会社の株式については、その種類や取得時期、経営への関与度合い等考慮しなければならない事情が多くあります。
2.1 株式が財産分与の対象となるケース
一般的に、婚姻期間中に取得した会社の株式は、財産分与の対象となります。
例えば、夫婦の一方が会社を経営し、他方が専業主婦(夫)であった場合、経営者の配偶者は、家事や育児を通じて会社経営を間接的に支えてきたとみなされ、会社の株式も共有財産の一部と捉えられます。
たとえ配偶者が会社経営に直接関与していなかったとしても、婚姻期間中に増加した株式の価値は、夫婦共同の努力による成果と見なされるため、財産分与の対象となる可能性が高いです。
2.2 株式が財産分与の対象とならないケース
一方で、婚姻前から所有していた株式や、相続や贈与によって取得した株式は、原則として財産分与の対象外となります。
これらの株式は、婚姻期間中の夫婦共同の努力によって得られたものではないと判断されるためです。ただし、婚姻後にこれらの株式の価値が著しく増加した場合、その増加分については財産分与で考慮される可能性があります。
例えば、婚姻前に相続した休眠状態の会社の株式が、婚姻期間中に経営努力によって大きく成長した場合、その増加部分については財産分与で考慮されるケースも考えられます。
もっとも、このような場合でも、配偶者が、会社経営にはほとんど関与していない場合は、財産分与で考慮されず、原則どおり財産分与の対象外とされる可能性があります。
株式が財産分与の対象となるか否かは、個々のケースによって判断が異なるため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、夫婦の状況や会社の状況を詳しくヒアリングし、適切なアドバイスを提供できます。
-
3.財産分与における会社の株式の評価方法
会社の株式が財産分与の対象となる場合、その評価方法もまた重要なポイントとなります。株式の種類等によって評価方法が異なるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。
3.1未上場株式の場合
未上場株式とは、証券取引所に上場されていない株式のことです。
未上場株式の評価は、取引市場がなく時価がないため、評価が難しく、複数の評価方法を組み合わせて行われることが多いです。主な評価方法としては、以下の3つが挙げられます。
・純資産価額方式:会社の総資産から総負債を差し引いた純資産を発行済株式数で割ることで、1株あたりの価値を算出する方法です。未上場株式は市場で取引されていないため、時価を把握することが難しいためです。
・類似会社比較法:同業種の上場企業の株価を参考に、類似企業の平均的な企業価値をもとにして、対象企業の企業価値を算定する方法です。財務状況や事業規模などが類似している企業を選択することが重要です。
・DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法):将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて、企業価値を算出する方法です。将来予測に基づくため、専門的な知識と分析が必要です。
これらの方法を単独で用いたり、複数の方法を組み合わせて、より適切な評価額を算出することになりますが、相手の納得を得るためには、専門家による評価、そして鑑定書のようなエビデンスが必要になることが予測され、税理士や会計士といった専門家の協力が必要になります。
3.2 上場株式の場合
上場株式とは、証券取引所に上場されている株式のことです。上場株式は市場で日々取引されているため、評価は比較的容易です。財産分与の時点(離婚時)における市場価格(時価)を基準として評価することになります。
-
4.経営する会社の財産は財産分与の対象となるか
会社経営者の離婚における財産分与では、株式だけでなく、経営する会社の財産についても財産分与の対象とすべきといった主張がなされることがあります。
会社の財産は、経営者個人の財産とは切り離されているため、会社の財産は財産分与の対象とはならないのが原則です(経営者が保有する会社の株式が財産分与の対象となり得ます。)。
もっとも、経営者個人の財産形成に会社の財産が影響を与えている場合は、財産分与の金額に影響する可能性があります。
4.1 会社の財産は財産分与の対象とはならないのが原則
会社は、経営者個人とは別に権利義務の主体となり、財産を保有することができます。この権利義務の主体となり、財産を保有する資格を「法人格」といいます。
会社は、経営者個人とは別に法人格を持つことになっており、会社の財産は、経営者個人の財産とは切り離され、会社のモノになるため、会社の財産は財産分与の対象とはならないのが原則です。もっとも、婚姻後に夫婦の共有財産を拠出して設立された会社である場合には、経営者が保有する会社の株式が財産分与の対象となります。
このように、夫が経営する会社の財産は、財産分与の対象とならないのが原則です(但し、夫が会社から受け取る役員報酬や退職慰労金は、サラリーマンの給与や退職金と同様、財産分与の対象となります。)。
4.2 会社の経費で支払われているもの
もっとも、経営者個人の財産形成に会社の財産が影響を与えている場合は、財産分与の金額に影響する可能性があります。
例えば、中小企業の場合、会社の経費で購入した車を自家用車として使用している場合なども往々にしてあり得ます。
会社の経費で購入している以上、原則は会社のモノであるため、財産分与の対象とはなりませんが、実質的に夫婦の生活費や個人的な支出に充てられていた場合は、財産分与の対象となる可能性が高まります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・社宅:会社が所有する住宅を、経営者とその家族が居住用に無償または低額で利用している場合。
・自家用車:会社名義で購入した車を、主に私用で使用している場合。
・生命保険料:経営者本人を受取人とする生命保険料を会社が負担している場合。
これらの支出が財産分与の対象となるかどうかは、個々のケースによって判断されます。
支出の目的、金額、夫婦の生活状況などを総合的に考慮して判断されるため、専門家である弁護士に相談することが重要です。
会社の財産と財産分与の関係は複雑であり、個々のケースによって判断が異なります。適切な財産分与を行うためには、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。特に、会社の経費が私的に流用されている場合には、証拠を収集し、適切な主張を行う必要があります。
-
5.財産分与をスムーズに進めるためのポイント
財産分与は、離婚に伴う精神的な負担に加え、離婚後の生活に関わる重要な金銭問題も絡むため、長期化してしまうことも少なくありません。
円滑に進めるためには、事前の準備や適切な対応が重要です。ここでは、スムーズな財産分与のためのポイントを解説します。
5.1 早期の弁護士への相談
財産分与について少しでも不安を感じたら、早めに弁護士に相談することが大切です。
一般の方にとって、離婚は一生に一度あるかないかの一大事ですが、弁護士は、離婚案件を多く取り扱うことによって、離婚において生じる法的な問題を多く経験しています。
その経験から、財産分与に関する裁判手続での考え方やその手続きをよく理解しており、離婚案件における裁判所の考え方をベースに、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
特に、会社の株式が関係する財産分与は複雑になるケースが多いため、弁護士をはじめ、税理士・会計士といった専門家のサポートは重要です。
弁護士への相談は、情報収集の段階から行うのがおすすめです。
財産分与の分与割合は、夫婦2分の1ずつという「2分の1ルール」が離婚実務上定着しています。
したがって、財産分与の金額を増やすためには、財産分与の対象となる財産をいかに把握できるかが最重要課題になります。
相手に財産を隠されてしまった場合、それを探し出すのは至難の業です。情報収集の段階から弁護士に相談することで、可能な限り財産分与の対象となる財産を把握できるようになります。また、弁護士に相談することで、精神的な負担も軽減されます。
精神的負担の大きい離婚案件は、なるべく早期に弁護士に相談することが賢明です。
5.2 夫婦間の話し合い(協議)
財産分与は、まず夫婦間の話し合い(協議)によって解決を目指します。協議で合意に至れば、財産分与を含めた離婚協議書(離婚合意書)を作成します。
財産分与を受ける場合には、強制執行認諾文言付公正証書にすることで、もし相手が支払いをしない場合には、裁判手続を省略していきなり相手の財産を差し押さえることができるようになります。
なお、協議の際には、冷静に話し合いを進めることが重要です。感情的になると、建設的な議論ができず、合意に至るのが難しくなります。
難しいところではありますが、できる限りお互いの主張を尊重し、歩み寄る姿勢を持つことが大切です。具体的な金額の話をする前に、ある程度落としどころを決めておくべきです。
どうしても冷静に話をするのが難しいと感じる場合には、弁護士へ依頼することや離婚調停を提起することも視野に入れるべきです。
5.3 離婚調停
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、調停委員という第三者が間に入り、夫婦間の合意形成を支援します。
調停で合意が成立すれば、調停調書が作成されます。調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、強制執行も可能です。
5.4 離婚訴訟
調停でも合意に至ることができない場合は、離婚訴訟へ移行せざるを得ません。離婚訴訟では、お互いの主張や立証を前提に、家庭裁判所が財産分与の内容を判決で決定します。
判決に不服がある場合は控訴することができます。
ただし、離婚訴訟は、離婚調停と比べても、どうしても時間と費用がかかってしまいます。できる限り離婚調停で解決できることが望ましいといえます。
-
6.財産分与で揉めないための対策
財産分与は、離婚に伴う大きな争点の一つです。
後々のトラブルを避けるためには、事前の対策が重要です。具体的には、婚姻前の契約や婚姻中の適切な財産管理が有効です。
6.1 婚姻前の契約
婚姻前に、将来の財産分与について取り決めておくことで、離婚時の紛争を予防できます。
婚姻中に得た財産は、夫婦の共有財産となるのが原則であり、財産分与の対象となりますが、婚姻前に財産分与の方法や対象財産など、具体的な内容を契約で定めておくことができます(民法755条参照)。
もっとも、この契約の内容を、第三者に対しても主張できるようにするには、婚姻の届出前に登記をする必要があります(同756条参照)。
6.2 婚姻中の財産管理
婚姻中における適切な財産管理も、財産分与のトラブル防止に繋がります。以下の点に注意しましょう。
①入出金の管理
夫婦それぞれの収入を明確にするために、それぞれが保有する口座を明確にしておくべきです。また、家計を管理する共有口座を作る場合は、その使途を明確にしておくことが大切です。家計簿をつける、出金記録を残すなどの工夫も有効です。メモ書きでもいいので、家計のお金の流れはその都度把握しておきたいところです。
②財産の記録
不動産や株式などの財産の取得時期や金額を記録しておくことで、財産分与の際にスムーズな話し合いを進めることができます。契約書などは大切に保管しておきましょう。
はじめから離婚するつもりで結婚する夫婦はいませんが、もしもの時のために、家計のお金の流れは、相手任せにせず、双方で把握できるようにしておくことが重要です。
-
まとめ
この記事では、離婚時の財産分与において、経営する会社の株式や財産がどのように扱われるのかを解説しました。
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける手続きです。財産分与の対象となる財産は、預貯金や不動産だけでなく、株式や自動車なども含まれます。
ただし、婚姻前から所有していた財産や相続・贈与で得た財産は、原則として対象外となります。
経営する会社の株式が財産分与の対象となるかは、ケースバイケースです。婚姻中に夫婦の共有財産から取得した株式は、原則として財産分与の対象となります。
一方、婚姻前から所有していた株式や相続・贈与で得た株式は、財産分与の対象外です。
会社の財産については、原則は財産分与の対象とはなりませんが、例外的に会社の財産が経営者個人の財産と同視できるような場合には、ダイレクトに財産分与の対象となるかどうかは別の話ですが、財産分与として考慮される可能性があります。
財産分与をスムーズに進めるためには、早期に弁護士に相談し、夫婦間で十分に話し合うことが重要です。
また、離婚調停や離婚訴訟でどういった判断がされるかを十分に理解しておく必要があります。財産分与で揉めないためには、婚姻前の契約や婚姻中の適切な財産管理が有効です。離婚の二文字が頭によぎった場合には、将来の離婚に備え、事前の準備が重要になります。
当事務所は、離婚相談に限り、初回1時間無料とさせていただいております。離婚、特に財産分与については、事前の準備が重要です。少しでも不安に思うこと、聞いてみたいことがあればお気軽にご連絡ください。